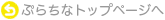■新世代アニソンシーンの誕生
――やはりアニメソングにおいては、作品そのものの影響はどうしても大きいんですね。
「作品との親和性の高さ」は、アニメソングを語るときに外せない要素ですね。
――その点で言うと、J-POPのアーティストがタイアップでアニメソングを歌うケースはどうなのでしょうか?
僕もまだまだ手探りで考えているところですが、たとえば昨年だと、Galileo Galileiが『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の主題歌を歌った例は、アーティストのファンにも、作品のファンにもすんなり受け入れられたように感じたんですね。それは、Galileo Galileiをど真ん中で聴いている世代は、アニメに対する抵抗感がいい意味で下がっているからだと思うんです。Galileo Galileiのメンバーたち自身もアニメをすごく好きなんですよね。たとえばドラムの子は『けいおん!』のファンだったりして(笑)。
――いい話ですね(笑)。逆にアニメファン側の抵抗がない理由は?
あまりいい言葉ではないかもしれませんが、カジュアルなアニメファンが今はすごく増えていて、とりわけ若い世代にはそういう子が多いんですよ。少なくともその子たちは、昔ほどタイアップソングとして作られたアニメソングに拒否反応はないですね。
――90年代はもっとアーティストと作品のミスマッチを感じることが多かったように思います。
『るろうに剣心』でJUDY AND MARYの「そばかす」が使われた当時は色々と言うひとも多かったみたいですね。ただ一方で、リアルタイムで『るろ剣』を観ていた当時の10代――今の20代後半~30代前半のアニメファンは、ちゃんとアニメソングとして受け入れてたりもしますよね。そういった世代間での考え方の違いもあれば、アニメを観ている人たちの全体に寛容さが広がっているところもありそうで、解釈は色々と複合的なんですよね。
――現状、アーティスト側からみて、アニメソングを歌うことにはどういった魅力があるんでしょうか?
アーティスト側から、いわゆる「アニメ枠」が熱望されているというのは、実感としてすごくあります。アニメの本数が2006年をピークに減りつつある一方で、世間的なアニメソングに対する評価や注目度の高さは上がっている。その流れの中で、メーカーさんもアニメの枠に新人をできるだけ投入していきたい流れは確かにあるんです。毎週同じ曲がテレビから流れるのは、それだけですごいプロモーション効果が見込めますし、アニメファンという通常のJ-POPリスナーとは違う新しい層に届くことも、J-POPサイドからすればいいことなんでしょう。そうした重要度の高まりに加えて、90年代の拒否反応を引き起こすようなタイアップ戦略の失敗を受けて学ばれているとも思います。アニメファンの心情をメーカーがきちんと研究されていますね。
――音楽業界レベルで、アニメソングに対する態度も変化していると。
どういうアーティストにどんな曲を書かせたらいいのか? というところで、昔みたいな乱暴な部分はなくなりましたね。メーカーさんの内側にもアニメファンが増えていることも大きいです。レコード会社がプロデュースする際に、ちゃんとアーティストにアニメ本編を観てもらって、原作も読んでもらってから曲を書いてもらう、ということをちゃんとやられています。考えてみれば当たり前のことなんですけど、そういった丁寧な仕事の積み重ねが実を結んできているのかなと思います。インターネットなどでネガティブな論評が広まってマイナスプロモーションになってしまったら、アーティストの死活問題にも繋がりますしね。
――作品を理解して、親和性を高めることがプロモーションに繋がる時代なんですね。アーティストやアニメタイトルとして象徴的な作品は何でしょう?
J-POP側からアニソンに対する回答として、ここ10年で一番パワーがあったのは宇多田ヒカルの「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」とのタイアップじゃないかと思います。トップアーティストとして活躍中だった宇多田ヒカルが、アニメ作品への理解を歌詞や楽曲で忌憚なく標榜して、音楽作品として主題歌を作り上げて、それをユーザーも好意的に受け止めた。90年代を象徴する大ヒット作である『エヴァ』の新作と、当時J-POPで最も影響力のある存在のひとりだった宇多田ヒカルが真っ正面からコラボレーションして、成功したというのは、振り返って今に繋がる流れとして見るとすごく重要だったんじゃないかと思います。確実にアニメソングの考え方を変えてくれたと思いますね。
――なるほど。作品に付随するという意味では、『機動戦士ガンダムSEED』などTBS土曜6時枠のなども大きかったのでは? T.M.Revolutionのような大物アーティストがアニメの主題歌を全力で手がけたことの影響は少なくなかったような。
T.M.Revolutionの西川貴教さんも、元々すごくアニメ好きだったんですよね。『SEED』に関しては、福田己津央監督が西川さんに直接お会いして、依頼されたとか。そのときに、西川さんをモデルにしたキャラクターを作中に登場させるというお話を監督がされて、アニメ好きで「ガンダム」シリーズもお好きだった西川さんは、「そこまで言っていただけるなら」ということで、作品のイメージにご自分を限りなく近づけるという手法で主題歌を作られたと。一方で、西川さんの例とは逆に、アニメソングからメジャーへの道を歩む現象もあったんですよね。90年代後半くらいから、アニメファンがこっそり楽しんでいたアーティストが、メジャーな場に出てくるようになったんです。
――例えばどういった方ですか?
特に言えるのは、菅野よう子さんですね。活動初期の頃からすごくいい劇伴音楽を作られていて、坂本真綾のプロデューサーとしても一流の仕事をされていたにも関わらず、最初期は軒並みCDが売れていないんですよ。それでも、アニメソングやアニメのファンからすると、大切なクリエイターだったわけです。表には出て来ない、狭い世界かもしれないけれども、ファンたちは思いを育てていた。狭い世界だからこその「これが俺たちの文化だ!」という意識をユーザーが共有できていたところもあって。
――それが今では、紅白をはじめNHKで引っ張りだこになるほどの大作家になられていうわけですよね。アニメソングの世界で、菅野さんのような、特異性のある音楽が生まれてくるルーツはどこにあるのでしょう?
『R.O.D -READ OR DIE-』や『ベン・トー』などの劇伴を手がけている岩崎琢さんとお話する機会があって、そこで気づいたことがあったんです。岩崎さんと菅野さん、あと、『Fate/Zero』の梶浦由記さんはほぼ同世代で、80年代に日本で起こった、ワールドミュージック(民族音楽)や、ピーター・ガブリエルに代表される民族音楽の影響下にあるロックのムーブメントをくぐってきているんです。ただそれは世代的な物の見方で、菅野さんはそういう文化とは無縁で天然な部分もかなりあるんですけどね(苦笑)。つまり、最もスノビッシュな音楽を集める文化発信基地だった頃の六本木WAVEを体験していて、そのあとに起こった、バブル期の喧騒も横目に見てきている。バブルの頃の日本というと、過剰でどぎついイメージがありますけど、お金があったから気持ちも寛容で、いろんな文化を発信できた時代でもあるんですよね。世界で500枚も売れない音源を「これが世界の音だ」と売り出せていたような時期。そこで青春を過ごされた音楽家たちは、すごく雑食なんですね。梶浦さんも少し特別で、彼女は少女時代をドイツで過ごされていて、ダイレクトにヨーロッパのワールドミュージック・ブームやニューエイジ・ブーム、スティーヴ・ライヒ、コクトー・ツインズらが所属した4ADと言ったマニアックなインディー・レーベルのロックを通過されていたそうですが。
※六本木WAVE……多くの音楽マニアから高い支持を得ていたレコードショップ。1999年に閉店。
――なるほど。その雑食な嗜好は、日本のアニメ作品が持つ特異性にもつながる部分があるような。
日本のアニメーションは何でもありですからね。アニメ作品として成立していれば、日本の伝統文化に乗っ取ることがかならずしも求められない。文化背景を背負わなければいけない傾向のある欧米のアニメーションとは違うところですよね。そういったアニメーションの自由な環境が、菅野さんをはじめ優れた音楽作家を自由にのびのびと活動させることができたんですね。岩崎さんは「極東文化のいい加減さ」とおっしゃっていたんですけど(笑)。今でこそ日本のアニメーションは世界にいろんな影響力を持っているけれど、我々自身は何の伝統文化も持ち合わせなくていい、明治時代にそういったことを捨ててしまった人種であると仰っていて。だから、アニメソングとして気持ちいい文法さえ合っていればいい。作品の物語や設定、キャラクターに合致してさえいれば、どんな音楽でもいい。そういったアニメの寛容な部分が、音楽と影響しあっているんじゃないかと思いますね。例えば『ベン・トー』では、フリージャズの曲もあればハードコアの曲もあって、民族音楽調のものもポリリズムを使った曲もある。そういった楽曲が、「半額弁当を奪い合う」というお話の劇伴として使用されて、評価されている。現象として本当に面白いですよね。
――そういえば『キルミーベイベー』の「キルミーのベイベー」に驚かされたんですよ。音楽好きのツボを押さえた曲なので、書いている人を調べてみたらEXPOで、演奏にはウンベルティポの今堀恒雄さんも参加されているという。
「本物」な人たちが作られたアニソンですよね(笑)。『ベン・トー』にしても、ドラムは吉田達也さんですし。「本物」をいきなり連れてきてもうまくハマるという、それこそがアニメの寛容な部分だなと思いますね。ただ、寛容さがある反面、文法は決して間違えられないという、制約が厳しい部分もあるので。1分29秒という尺もそうですし、主題歌としての意味を持たせなければいけないし。そこがうまくできていないと、ユーザーも説得力を感じてくれない。
※EXPO……87年に結成された松前公高と山口優による音楽ユニット。
※吉田達也……ロックバンドRuinsをはじめ、様々なバンド・ユニットで活躍しているドラマー。
――そこがまた、アニメソングを考える上では難しいですよね。たとえば、冨田さんがアニメソングとしての「文法」をうまく押さえていると感じた最近のタイトルを挙げていただけると、「文法」というものがイメージできるのかと思うのですが。
最近の作品だと『Steins;Gate』のOP曲「Hacking to the Gate」は良かったですね。原作ゲームを遊んだ方は主題歌の歌詞にいろんなキーワードが散りばめられていることに気付くんですが、アニメ版から入った方には最初は何のことかさっぱりわからない。でも物語が進んでいくと、「ああ、こういうことだったんだ」とわかってくる。しかも2コーラス目は終盤の物語の展開に合わせてあって、23話でいきなりOPで使われる箇所が変わるんですよね。そういった作品の演出との合わせ方がすごいと思いましたね。